【学校紹介】都立三鷹中等教育学校 前半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.145
東京都立三鷹中等教育学校
三鷹市新川6-21-21
『思いやり・人間愛を持った社会的リーダーの育成』
共学校

統括校長 小林 正人先生
👇👇👇インタビュースタート👇👇👇
✐✎✐✎まずは✐✎✐✎
Q1:2009年(平成21年)に創立され、今年で16年目になりますが、現在各学年何クラスあり、何名在籍していますか。
A1: 1クラス40名、各学年4クラス、全学年24クラス、1クラス40名
Q2: 現在の男女比を教えてください。
A2: 933名です。2年生から6年生までは男女別定員制で5:5です。1年生からは男女合同選抜制となり少し女子が多くなっています。ただ、受検はどうなるか分かりません。また来年度から公立の中学校は35人学級になるので、定員は20人減ります。今後、男女比も変わるかもしれません。
Q3: 教育理念『思いやり・人間愛をもった社会的リーダー』を育てることを目的にしていますが、どのような取り組みを行っていますか。
A3: 人間性の育成に焦点を当てています。教科学習はもちろんですが、学校行事と部活動を活発に行っています。学校行事や部活動では、様々なやくわりを狙いそれを全うして責任を果たしたり、異学年同士の生徒が試行錯誤し切磋琢磨したりすること、それも全力で取り組むことで、生徒の人間性が一回りも二回りも大きくなっていきます。
これからの時代には勉強だけでなく、『主体性』『我慢する力』『バイタリティ』『多様性を尊重する』『知的好奇心を持ってさまざまなことに挑戦する力』など幅広い力が求められるようになります。本校では、教科学習を軸としながら、こうした力を育むことを教育理念としています。
Q4:自転車で通学することはできますか。
A4: 前期課程の生徒(中学生)は禁止ですが、後期課程の生徒(高校生)は可能です。
Q5:どのエリアから通ってくる生徒が多いですか。
A5:三鷹市、調布市、世田谷区、杉並区、武蔵野市の生徒で2/3です。生徒の中には、葛飾区や江戸川区、港区から通学している生徒もいます。
Q6:東京都教育委員会より「デジタルを活用したこれからの学び研究校」に指定をされていますが、どのような取り組みをしていますか。
A6:授業スタイルを根本的に変え、先生が伴走者となって生徒が主体的に学ぶことができるような授業を開発する指定校です。これは激しい時代に向けて、『自立した学習者』になれるよう、生徒が見通しをもって学習のゴールを設定し学習計画を立て主体的に学ぶ、最先端の授業方法になります。この指定は、都内公立小・中・高約2060校あるうちのわずか10校しか指定されてないハイレベルの指定校になります。
なお、「デジタルを活用したこれからの学び研究校」という名称のとおり、「デジタル活用」よりも、「これからの学び」の在り方そのものに重点が置かれている点が特徴です。
✐✎✐✎基礎知識・技能・学力✐✎✐✎
Q7: 1年生から6年生まで、コース分けをしていますか。
A7:していません。1年生から5年生まではほぼ同じカリキュラムになり、6年生は生徒自身の進路に合わせて、選択科目を受講します。
Q8:先取り学習をしていますか。
A8:本校は中高一貫校のため、先取り学習は可能ですが、私立校のように「6年間の内容を5年生までに終わらせ、6年生は入試対策に専念する」といった形は取っていません。あくまで「緩やかな先取り学習」を行っています。
一見、先取り学習は良いことのように思えますが、進度についていけない生徒が増える可能性があり、その結果、転学を選ぶ生徒も出てきてしまいます。そうした事態を避けるためにも、無理のない範囲で、全員がしっかり理解できるように配慮した、緩やかな先取り学習を行っています。
Q9: 少人数授業や習熟度別授業を行っていますか。あればどの教科で行っていますか。
A9: 本校では英語と数学で、1年生から5年生まで2クラス3展開の習熟度別授業を行っています。
Q10:『文化科学』『自然科学』『文化一般』という独自科目があり、探究学習を実施していますが、何年生が、どのように行っていますか。
A10: 『文化科学』は1・4・5年生で、『自然科学』は2・3・6年生で、『文化一般』は1年生で実施しています。
たとえば、『文化科学』では、小倉百人一首の中から自分の好きな一首を選び、その歌を詠んで思い浮かんだ情景を絵に描きます。次に、その歌が詠まれた時代背景について調べてまとめ、最後にその歌の解釈や自分の思いを1枚の紙にまとめます。これは、美術・歴史・国語といった複数の教科を横断する学びとなっており、生徒にとって将来必ず役立つ力を育む内容になっています。
Q11:3学期に行われている『知の文化祭』とは、どのようなものですか。
A11:探究発表会のことです。本校では、1年生から5年生までが参加します。1年生から3年生はグループ発表、4・5年生は個人発表になります。3年生は動画による発表になりますが、それ以外の学年はA0の大きさのポスターを作成して、ポスターセッション形式で全員が発表します。
探究学習のテーマは、生徒自身が自由に設定します。選ばれるテーマは多岐にわたり、学術的なものからサブカルチャーに関するものまで、360度さまざまな分野に及びます。こうした多様性を反映し、生徒自身が『文化祭』と名付けました。
具体的な探究内容としては、1年生は地元についての探究、2年生は校外学習で訪れる長野県白馬村をテーマに「白馬村をより活性化させるにはどうすればよいか」を考えます。3年生は、前期に理系10テーマ、後期に文系10テーマの中から1つを選び、グループで研究を行います。
4年生からは、文系・理系を問わず、自分で選んだテーマで1年間の個人研究に取り組みます。5年生では、4年生での研究をさらに深めることも、新しいテーマに取り組むことも可能です。6年生になると、5年生で行った研究を論文としてまとめます。
『知の文化祭』は、生徒主体で運営されています。実行委員がすべての企画・運営を行い、体育館や剣道場に衝立を立ててポスターを掲示し、発表を行います。
近年では校外で発表する生徒も増えており、『日本地理学会 理事長賞』や『高校生国際シンポジウム 生物分野ポスター部門 最優秀賞』などを受賞する生徒もいます。私たちは何より、生徒たちが「探究したことを発表するのが楽しい」と感じていることを、とても嬉しく思っています。
Q12: 御校の授業の特徴があれば、教えてください。
A12: 本校では、講義形式の授業とともに、生徒がゴールを定めて自ら学ぶ主体的学びやグループで話し合う主体的な学び、そして実験・フィールドワークなど体験的な授業も盛んです。いずれの授業でもパソコンを多用しています。
卒業後、パソコンを使わない日はおそらくないだろうと考えており、在学中から積極的に活用しています。ただし、本校の目的はICT技術者を育成することではなく、あくまでパソコンを「学びを支える道具」として位置づけています。
生徒は日常的にパソコンを持って職員室を訪れ、先生と画面を共有しながら質問や議論を交わします。また、課題の提出や共有、クラスメイトの進捗状況の確認、情報の参考にするなど、多様な形で活用しています。
Q13:月曜日の放課後に行われている補習は、どのように行われていますか。
A13:昨年度から月曜補習は中止し、適宜平日や土曜日に補習を実施しています。
Q14:春期・夏期・冬期講習はありますか。あれば何講座くらい準備されていますか。
A14: ありますが、学期中も随時実施しています。昨年度は年間通して全部で132講座実施しました。
基礎学力の定着を目的とした補習は、必要に応じて参加を促す(半ば強制的な)ものもあります。一方で、フィールドワークなどの体験型講座は希望者を募って実施しています。
教科の学びを深める講座や、大学入試を見据えた講座も、もちろん用意しています。
Q15:チューター制度はありますか。
A15:ありませんが、自習室には「学習支援委員」として卒業生が来てくれています。生徒は、彼らに学習の相談をしたり、勉強を見てもらったりすることができます。
Q16:中高一貫教育のメリットは何ですか。 A16:6年間の一貫した教育が可能ですので、生徒の理解度に応じて、発展的な内容にも取り組めること、高校受験がないので、学校行事や部活動にじっくり取り組めることです。
👇後半はコチラ👇
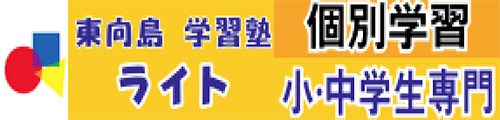


“【学校紹介】都立三鷹中等教育学校 前半 インタビュー” に対して3件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。