【学校紹介】東京都立三田高等学校 前半(インタビュー)

学校紹介:インタビューNo.113
東京都立三田高等学校
港区三田1-4-46
【Have Wings and Fly High=
教養・探究・立志そして世界へ】
共学校

校長 内田 隆志先生
👇👇👇インタビュースタート👇👇👇
✐✎✐✎まずは✐✎✐✎
Q1:1923年(大正12年)に創立されたということで、今年度で100年周年ですね。
A1: 大正12年に設立されましたので、今年の6月9日に100周年の式典を行いました。
Q2:現在各学年何クラスあり、在籍は何名ですか。
A2:1年生が8クラス、2年生が7クラス、3年生が7クラスあります。来年はまた7クラスに戻ります。在籍人数は1年生317名、2年生265名、3年生277名です。
Q3: 昨年度20%の男女枠緩和がありましたが、男女比はどのくらいですか。
A3:1年生は若干女子生徒が多く6:4、2・3年生はだいたい半々です。
Q4:来年度から男女共通定員へ移行しますが、男女比がどのようになると予測をしていますか。
A4: 3:2で女子の方が多くなるのではないかと、予測しています。国際も7:3で落ち着いていますので、その程度で、落ち着くのではないかと考えています。教育研究関係の方からいただいた模擬試験の第一志望の人数割合のデータを見てみると6:4になっていました。ただ合格ラインに達しているかどうかになると別の話になります。受験生の皆さんも気になるところだと思いますが、我々も気になる部分です。
男子生徒が活発な小山台や駒場と比べられることが多いですが、三田高校に入学する生徒はどちらかというと穏やかな子が多いので、自分に合った学校を選ぶという意味ではあまり変わらないと思っています。
Q5:『新しい時代の課題解決の対応し、社会貢献できる人材育成』を目指して教育活動をしているようですが、具体的にどのようなことを行っていますか。
A5: 2つの大きな柱があります。1つは国際理解教育、もう一つは探究学習や課題研究です。国際理解教育では、本校はユネスコスクールにも指定されています。様々な形で海外交流、あるいは日本にいる外国籍や外国にルーツを持つ方との交流を通して、生徒が多様な考えや世界の状況について自分自身で理解し、肌で感じられるところが一番大きいところです。もう一つは探究活動です。4代前の校長 及川良一先生の頃から全国の学校に先駆けて探究学習を行っています。1・2年生は、自分のテーマを見付けてそれに関して研究をしていきます。最終的に2年生の段階で4千字の論文を書きます。この取り組みに関して、単に教科・科目に帰着するのではなく、教科横断的な視野を作ることによって、社会の課題や自分の興味を突き詰めていく力がつくと考えています。大学や社会でも研究する力や自ら積極的に取り組む力が求められています。実際に国際交流と探究学習は、親和性が高く、本校が積み重ねてきた大学進学実績などの成果はそのことが一番の要因ではないかんと考えています。
Q6: 自転車で通学することはできますか 。
A6: 基本的には都心ですので自転車で通うことが危ないので、自転車通学はできません。
Q7: どのエリアから通ってくる生徒が多いですか
A7: 大田区が一番多いです。次に江戸川区、足立区、品川区、世田谷区の順になります。都内全域から来ています。山手線・京浜東北線・都営三田線・都営浅草線・さらに大江戸線など多くの路線が使えますので、そういった面では、通いやすい場所になります。
✐✎✐✎東京都指定校✐✎✐✎
Q8:東京都教育委員会より『進学指導推進校』に指定されていますが、どのような取り組みを行っていますか。
A8: まずは国公立大学への進学対応型のカリキュラム、また土曜授業や受験に対して様々な大学に対応できるきめ細やかな指導を中心に行っております。定点観測ということで定期的に模擬試験を実施して、その模擬試験に関しての分析や分析をすることで、さらに学力の引き上げをする取り組みをしています。変わったところでは、今年から校内予備校ということで、墨田川高校・江北高校と本校が同じ業者で実施しており、エデュケーショナルネットワークさんが入り、土曜日や不定期ですが講習をスタートしています。生徒たちがいろんな機会を得ることは、刺激になりいい事だと思っています。これは無料で受講することができます。都全体の進学の底上げ、また経済的な負担の軽減を兼ねて実施しています。本校は、「都立図書館連携推進校」にも指定され、都立中央図書館とも連携しており、主体的な学びを東京都教育委員会も含めて支援しています。
Q9:英語教育に関して多くの推進校になっていますが、在校生たちの利点を教えてください。
・Global Education Network20(GE-NET20)
・国際交流リーティング校
・海外学校間交流推進校
A9: 例えばGE-NET20では、20校が指定されています。定点観測として英検2級程度を受検することになっていますが、その1回分の試験料を都が負担しています。また英語教育に特化して指導をしていますので、通常の高校よりは、英語教員が2名多く配置されています。授業次数も3年間で、必修が17時間となり、若干多くなっています。英語を中心として指導体制が整っていることが、生徒にとって大きなメリットだと思います。
コロナ前ですと、カナダや台湾の学校と姉妹提携をしておりました。台湾の大同高級中学校(台湾の高校)との交流は、オンラインで継続的に行っています。今後は、コロナも明けたので、海外へ戻す予定になっています。大同高級中学校をはじめとして、姉妹校の交流も再開したいと考えています。本年度はこのほかに、オーストラリアのスタディツアーを受入れ、海外の高校生と直接交流をしたり、カザフスタンやユネスコの国際会議の教育視察団を受入れ、生徒が英語で訪問された方との交流を行ったりすることができました。様々な、経験は自信と新たな挑戦につながるものだと思っています。
Q10:TOKYO教育DX推進校に指定されていますが、どのようなことを行っていますか。
A10:それはパソコンを活用したデジタル教育です。今年より都立高校全体で、タブレット端末を購入していただき活用することになり、それを特に推進する学校として指定されました。成績処理でパソコンを使用し、より効率的な採点をし、その採点をした結果で、『生徒ができなかった部分を見て授業の改善』をしたり、『活用するためにどのような取り組みが必要か』また『他校と繋ぎ、オンラインでのやりとりや研究発表をしたり』『探求の発表は生徒が端末を活用しプレゼンテーションをしたり』しています。小学校・中学校でタブレットを使うようになりましたので、デジタルネイティブ世代に通用するような技術を身につけながら教育をすることが大きな狙いになっています。
✐✎✐✎基礎知識・技能・学力 ✐✎✐✎
Q11: 少人数授業や習熟度別の授業はありますか。
A11: 本校は毎年20名ずつ海外帰国生の入試を実施しています。この生徒たちには学習のサポートが多少必要な場面がありますので、1年次の国語・家庭科や2年次の英語・数学、3年次の英語は習熟度別にしています。
Q12:長期休み期間中に講習はありますか。あれば、どのくらいの講座をどのように行っていますか。
A12: 3年生には受験向けの講座、1・2年生には基礎講座を夏期講習だけでなく冬期講習も行っています。希望制で講座を選択して受講しています。
Q13:生徒全員が6教科7科目の授業を行っているのでしょうか。クラス分けなどで教科を絞りますか。
A13:毎年クラス替えをしています。1・2年次は一部の理科・社会で選択し分かれますが、3年生になると自分自身の将来を見据えて、文系理系の選択になります。基本的には全員が6教科7科目について学ぶ形で国公立を目指すことができるような状態を作りだしています。
Q14:チューター制度がありますか。
A14:本校では『自主学習を支援するサポーター』と呼んでいますが、毎年10名程度の医科歯科大学・慶応大学・早稲田大学・立教大学などの本校の卒業生の先輩が、進路についての指導や教科の質問にも答えてくれています。職員室前のテーブルのところで常に待機していますので、教えてくれています。
Q15: 自習室はありますか。
A15: 大きな食堂があります。また校内のいたるところに机と椅子が置いてあるので、そこで学習することができます。
Q16: 学校は何時まで残ることができますか。
A16: 18時まで残って学習することができます。時間を区切ることで、集中してすることができます。部活動もそうですが、学校によっては時間を延刻して行っているところもありますが、『限られた時間をいかに有効に使うか』を学習のモットーにしています。
続きはコチラ👇
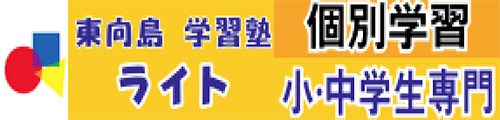


“【学校紹介】東京都立三田高等学校 前半(インタビュー)” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。