【学校紹介】都立桜修館中等教育学校 前半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.147
東京都立桜修館中等教育学校
目黒区八雲1-1-2
『真理の探究』
共学校

統括校長 信岡 新吾先生
👇👇👇インタビュースタート👇👇👇
✐✎✐✎まずは✐✎✐✎
Q1:旧制府立高等学校、東京都立大学附属高等学校を前身とし、2006年(平成18年)に中等教育学校として新たに創立され、今年で20年目を迎えます。現在、各学年は何クラスあり、何名が在籍していますか。
A1: 各学年4学級、全体で24学級あります。5月1日現在の在籍者数は942名です。一学年は160名ですが、留学している生徒もいます。都立の中高一貫教育校には、一度転校(ご家庭の転勤や留学のため)しても戻れる制度があります。
通常の都立高校では転校や退学があると、その席を募集で埋めますが、中高一貫教育校では行いません。そのため、在籍数は若干少なくなっています。
Q2: 現在の男女比を教えてください。
A2: 今年から男女枠が撤廃されましたが、全体(942名)のうち男子425名、女子517名で、女子のほうが多く在籍しています。本校の名前「桜修館」もあり、昔から女子に人気のある学校です。男女枠があった時も、繰り上げ合格の場合は女子が入学するケースが多く見られました。
割合は男子45%、女子55%で、極端に女子が多いわけではありません。
Q3: 「6年間の一貫した教育活動の中で、世界の中の日本人としてアイデンティティを持ち、国際社会を担う人材を育成する」という教育方針を掲げていますが、具体的にはどのような取り組みを行っていますか。
A3:本校では国際理解教育に力を入れています。海外の学校との交流や海外派遣研修を実施しており、英語教育だけでなく、外国語教育も充実させています。第二外国語として、フランス語、ドイツ語、中国語、ハングル、スペイン語の中から選び、4・5年生(高校1・2年生)で学ぶことができます。2つの言語を浅く学ぶことも、1つの言語を2年間通して学ぶことも可能です。これほど多くの言語をそろえている学校は珍しいと思います。
また、「アイデンティティを持つ」という観点から、「思考力」「判断力」「表現力」を大きな柱としています。自己主張や説明など、自分の考えを持ち、多様な国や地域の方々と関わる力を、6年間を通して育成しています。
Q4:自転車で通学することはできますか。
A4: 東京都の基準に合わせ、前期課程(中学生)の生徒は自転車通学を禁止しています。後期課程(高校生)は、希望して届け出れば通学が可能です。
Q5:どのエリアから通ってくる生徒が多いですか。
A5:卒業した小学校の所在地で見ると、世田谷区と大田区の生徒が特に多く、次いで目黒区、品川区が続きます。また、江東区、港区、町田市からも通学しています。
✐✎✐✎東京都指定校✐✎✐✎
Q6:東京都教育委員会(都教委)より「理数研究校」に指定をされていますが、どのような取り組みをしていますか。
A6:理系の文化部に所属する生徒が主体的に活動できるよう、予算が配分されています。全国規模や世界規模のコンテスト・大会に出場する生徒も多く、その実績を活かして総合型選抜で大学へ進学するケースもあります。おととしの卒業生2名は、世界規模のコンテストで上位入賞を果たし、東京大学へ進学しました。
また、本校では理科・数学に加え、社会科の授業もカリキュラム面で非常に充実しており、他の中高一貫校には見られない特色となっています。授業内容にも工夫を凝らして展開しています。
✐✎✐✎基礎知識・技能・学力✐✎✐✎
Q8: 御校の授業の特徴があれば、教えてください。
A8:本校では探究学習の一環として、レポート作成の機会が多くあります。前期課程では「国語で論理」「算数で論理」という、本校独自に設定した教科を設けており、その活動が全教科に浸透しています。
授業は「聞いて問題を解いて終わり」という従来型ではなく、最後に論文やレポートとしてまとめる形を多くの教科で採用しています。教員も熱心に指導し、その集大成として各学年で研究論文にまとめることを行っています。このように、本校では文章表現力を養う機会が非常に多くあります。
Q9: 先取り学習をしていますか。
A9: 本校では、いわゆる先取り学習は行っていません。中学校では中学の内容を、高校では高校の内容を学ぶのが本来ですが、本校では中高6年間の学習内容を系統立てて並び替え、効率的に学習できるようにしています。
例えば数学では、三角形の学習の後に三角比を続けて学ぶことで理解がスムーズになります。一般的なカリキュラムでは、中学で直角三角形を学び、高校で三角比を学ぶ前に再び中学内容を復習しますが、本校では連続して学ぶことで効率化を図っています。その結果、6年間かける学習を1年短縮し、5年生で主要内容を終え、6年生は演習に専念できるのが基本形です。
もちろん進度が異なる教科もあります。数学は5月のゴールデンウィークまでかかります。理科と社会は、進学指導重点校と同様のカリキュラムを採用しており、国公立大学受験に強い構成になっています。理科は「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」に加え、「物理」「化学」「生物」「地学」も学ぶ内容です。社会も、地理A・地理Bが廃止され、新科目「地理総合」「地理探究」に再編されましたが、本校では「地理B」に相当する高度な学びを継続しており、6年生の秋までかかります。
本校の授業は、教科書を終えれば「受験勉強」や「塾の勉強」を改めてする必要がないほど緻密に組まれています。教員も深い内容まで指導し、常に研鑽を重ねています。他校にはないほど理科・社会が充実しているのが特徴です。
Q10:1年生から6年生まで、コース分けをしていますか。
A10:していません。
Q11:少人数授業や習熟度別授業は行っていますか。行っている場合、どの教科で実施していますか。
A11:英語と数学は、全学年で少人数制や習熟度別授業のいずれか、またはその両方で実施しています。
Q12: 前期課程の中で『倫理』の授業があると伺いましたが、具体的にどのような内容を学んでいるのでしょうか?
A12: 中学1年生から3年生まで、『国語で論理』『数学で論理』がそれぞれ1時間ずつ組み込まれています。
学年ごとにテーマが設定されており、
- 1年生:見つめる ~ 身近な地域を知る
- 2年生:広げる ~ 社会に目を向ける
- 3年生:見つめる ~ 3年間の学びと自分を振り返る
- 4年生:育てる ~ 自分の『探究テーマ』を見つける
- 5年生:深める ~ 自分の『好き』を深める
- 6年生:つなげる ~ 自分の『好き』を未来へ
調べ学習から探究へと発展させ、最終的には5年生で約5,000字の論文をまとめることが探究学習の大きな柱となっています。
4年生から本格的に探究活動が始まりますが、その基礎となっているのが前期課程の『国語で倫理を学ぶ』と『数学で論理を学ぶ』の授業です。
『国語で倫理を学ぶ』では、基礎的な文章の書き方から始まり、情報の扱い方、思考の視覚化、情報の信頼性の判断などを学びます。
一方『数学で論理を学ぶ』では、情報の分析や確率統計、データ分析など、データサイエンス的な内容を扱います。これらは理系分野の内容ですが、論文作成においては文系理系に関わらず、アンケートやデータ処理のために統計学の知識が必要となります。
このように、『思考力』『判断力』『表現力』を前期課程の3年間で体系的に身につけています。
その結果、国公立大学への現役合格率は47~48%に達し、浪人者を含めると50%を超えています。5~6割の生徒が国公立大学に進学する学校になることが必要であり、その需要も高いと考えています。
また、早い段階で文理選択を行い、それぞれに特化した教育をするのではなく、全教科をバランスよく学ぶ方針です。その結果、国公立大学進学が当たり前の道筋となる学校へと成長しつつあることが、本校の強みの一つであり、上述の教育内容がその基盤となっています。
Q13:探究の学習に力を入れていると伺いましたが、具体的にどのような形で取り組まれているのでしょうか?
A13:本校では、6年間を通した体系的なカリキュラムを実施しています。探究の時間は後期課程に設定されていますが、6年間で何を学ぶかは全て計画されています。最後は進路実現に向けた学習に取り組みます。
4・5年生からはオープンキャンパスへの参加を促し、今年度からは探究学習を学校内だけで完結させるのではなく、外部の場へ積極的に出る取り組みを進めています。
近年、大学やNPO、研究者が高校生向けのプログラムを開催しており、本校の土曜日は半分が休みとなっているため、生徒が早い段階からこれらに参加しやすくしています。生徒自身が主体的に情報を見つけ、行動できるよう、多くの情報や様々な素材を提供しています。
Q14: 春期・夏期・冬期講習はありますか。あれば何講座くらい準備されていますか。
A14: 夏期講習がメインで、約70講座を準備しています。人気の講座は大きな教室で実施しています。
冬期から春期にかけては、全体での講習というより個別対応が中心で、二次試験に向けた添削指導や過去問題対策を行っています。
Q15: チューター制度はありますか。
A15:東京大学や東京工業大学の学生が来ており、科学部や理数系の発表をする生徒に対して個別指導を行っています。
Q16: 中高一貫教育のメリットは何ですか。
A16:6学年あることが大きなメリットです。生徒同士のつながりが強く、本校は特に仲が良いと感じています。普通の学校では、5学年も年上の先輩がいることはありません。中学1年生の生徒は目を輝かせており、メンターや師範のように目標となる先輩が校内にいます。この環境は中高一貫校ならではのものです。
また、4学級という小規模さと6学年の体制も特徴です。5・6年生は下級生に配慮する姿勢が見られます。先日行われたクラスマッチ(体育祭)では、6年生が主役である一方、1・2年生の動きを優先して進行を組み立てていました。こうした下級生への配慮を学ぶ経験も、中高一貫校ならではだと思います。
このような経験が6年生にとって良い成長の機会となり、それが毎年繰り返されます。現在の6年生の実行委員が仕切る姿を見て憧れ、来年の実行委員が同じように活躍するという良いサイクルができています。
👇後半はコチラ👇
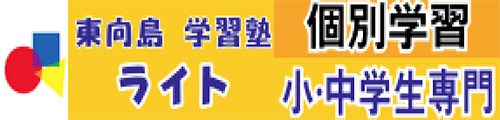


“【学校紹介】都立桜修館中等教育学校 前半 インタビュー” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。