【学校紹介】都立日比谷高等学校 前半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.142
東京都立日比谷高等学校
千代田区永田町2-16-1
『学問の本質に触れる楽しさ』と『知の創造』
共学校

統括校長 萩原 聡先生
👇👇👇インタビュースタート👇👇👇
✐✎✐✎まずは✐✎✐✎
Q1:1878年(明治11年)創立の、都立一番手校として伝統と歴史のある学校ですが、現在は各学年に何クラスあり、在籍生徒数はそれぞれ何名ですか。
A1:各学年8クラス編成です。在籍生徒数は、1年生が331名、2年生が318名、3年生が317名となっています。
Q2: 男女比を教えてください。
A2:ほぼ男女同数です。
- 1年生:男子165名、女子166名
- 2年生:男子155名、女子163名
- 3年生:男子166名、女子151名
3年生は男女別定員制での募集だったため男子が多く、2年生からは男女別定員制が撤廃され、ほぼ同数が入学しています。なお、本校では「休学」して「留学」する生徒が大半のため、学年により人数に若干の変動があります。
Q3: 『自律的人格』『学業と教養』『責任と協調』『心身の健康』『文化と平和』を教育目標に挙げ、21世紀を逞しく切り拓くグローバルリーダーとして活躍する人材を育成しているとのことですが、これらの目標を実現するために、具体的にどのような取り組みをされていますか。
A3:教育課程の工夫をはじめ、特別活動(学校行事、部活動など)やグローバル事業などさまざまな教育活動に取り組んでいます。
Q4:自転車で通学することはできますか 。
A4: 許可していません。
Q5: どのエリアから通ってくる生徒が多いですか
A5: 主な居住地は以下のとおりです。
- 世田谷区:120名
- 大田区:82名
- 練馬区:65名
- 江東区:57名
- 江戸川区:54名
自宅から本校までの通学に便の良い地域からの生徒が多い傾向にあります。
✐✎✐✎文部科学省・東京都指定校✐✎✐✎
Q6: 東京都教育委員会より『進学指導重点校』に指定されていますが、どのような取り組みを行っていますか。
A6:東京都教育委員会から進学指導重点校として、「難関国公立大学や国公立大学医学部医学科への進学を実現すること」を目標とすることが求められており、教員の1名加配や公募制が実施されています。
Q3の回答のように、さまざまな取り組みを行っています。
Q7: 『Tokyo Metropolitan Global Education Network School Premier 20』および『海外学校間交流推進校』に進学した在校生たちの利点を教えてください。
A7: 「Tokyo Metropolitan Global Education Network School Premier 20」(※今年度から名称変更、略称「GE-NET20」)に、再指定されました。本校では「人類の平和や社会の発展に貢献できるグローバルリーダーとしての素養を身につけること」を目標に掲げています。具体的な取り組みとしては、「グローバル委員会」に1・2年生の希望者が参加し、グループごとにテーマを決めて、その課題解決に向けた研究に取り組んでいます。国内研修では、校内での講演会のほか、日本企業や官公庁に訪問し、自分たちの研究テーマに沿った質問を行い、学びを深めています。また、2年生の希望者によるアメリカ研修(ボストン、ニューヨーク)も、円安やアメリカの物価高の影響で費用が年々高額となっていますが、今年度は21名で実施予定です。生徒たちは日本で研究した内容を、アメリカの大学(MIT、ハーバード大学)やアスペン研究所で提言発表を行い、指導助言を受けてきます。ニューヨークでは、国連本部や911メモリアルミュージアム、船上から自由の女神像、タイムズスクエアなどの見学も行っています。帰国後も研究を継続し、校内発表会に向けて完成させます。
「海外学校間交流推進校」については、本校では姉妹校締結をしている韓国のミチュホル外国語高校との学校間交流を行っています。ホームステイ型のプログラムで、韓国の生徒を本校生徒の家庭で受け入れ、その後、そのご家庭の生徒が韓国でホームステイをさせてもらうという形です。これは希望制で、毎年約15名の生徒が参加しています。この交流は、家族ぐるみで、「日韓文化交流」の要素が大きいです。
また、本校の隣にはメキシコ大使館があり、1年生全員が3月に招待を受け訪問し、メキシコ文化に触れる機会となっています。
Q8:文部科学省指定の『SSH(スーパーサイエンスハイスクール)』として行われている探究活動は、どのように行われていますか。(希望制・個人探究またはグループ・学年など)
A8: 本校はSSHに指定され現在第Ⅳ期目となり、「次世代の国際社会を牽引する、高度なデータサイエンス能力を有する人材の育成」を研究開発主題として、取り組んでいます。
プログラムとしては、1年生全員が教科「理数」において、「理数探究基礎」という科目に取り組みます。これは、他校の「総合的な探究の時間」における探究活動に相当します。テーマは「理数」に限定されておらず、データを活用したものであれば文系的な内容でも構いません。1年の2月にはポスター発表を行います。その活動を発展させる形で、2年生では自由選択科目として「理数探究」を選択することができます。1年生で取り組んだテーマを深める生徒もいれば、新たなテーマに取り組む生徒もいます。さらに、3年生では「理数探究発展」という科目を選択することが可能です。3年生では、学会主催の高校生向けの研究発表会に参加し、論文作成などを夏休み前まで継続して行います。その成果を大学への推薦材料とすることも可能なように、3年生前半で活動を終えるようにしています。
Q9:SSHによる海外研修や国内研修が実施されていますが、どのような生徒がこれらのプログラムに参加しているのでしょうか。
A9:昨年度まではアメリカでの海外研修を実施していましたが、引率教員の予算が限られる中で、生徒の興味・関心に応じた活動を行うにはアメリカ国内が広大で一度に複数地域を訪問するのが難しいことなど、さまざまな課題がありました。そのため、今年度からSSHによる海外研修は一時的に中止し、その代わりに国内研修を積極的に展開しています。研修先は、北海道、沖縄、福島、筑波研究学園都市、伊豆大島など、テーマに応じて選定された地域で行っています。これらの研修は、希望者が多数の場合は、書類選考や面接によって参加者を決定します。
たとえば、北海道では現地の高校生との交流活動を実施します。また、福島では、八王子東高校の生徒とともに現地を訪れ、原発問題についてお話を伺う予定です。八王子東高校はSSH指定校ではありませんが、このような取り組みを他校へ広げていくことも、SSHの役割のひとつと考えています。
✐✎✐✎英語力✐✎✐✎
Q10:英語教育で力を入れていることはありますか。
A10:本校では、GE-NET20の一環としてオンライン英会話を1年生全員に導入しているほか、ケンブリッジ英語検定を1・2年生全員が東京都教育委員会の助成により受験し、自らの英語力を測定する機会となっています。
英語教育において特に力を入れているのは、「読む・書く・聞く・話す」の4技能を総合的に育成することです。今春に卒業した生徒の大学入学共通テストでも、英語リーディングの平均点は93.8点と高い成果を上げています。受験英語だけに偏ることなく、総合的な英語力を身につけることで、入試においても良い結果につながっています。
授業では、入学時点ですでに高い英語力を持つ生徒が多いため、それをさらにブラッシュアップする授業を展開しています。実際に、入学時点で英検準2級を取得している生徒が多く、1年次のうちに多くの生徒が2級を取得しています。そのため、授業内容は教科書のほか、CBSニュース を素材としたリスニング教材や大学入試長文問題集などさまざまな教材を用いて、4技能を総合的に育成する授業を行っています。
週に1時間、1年生はディスカッションに、2年生はディベートに重点を置き、発信力を養うアクティブな英語の授業も行っています。
文法指導に関しては、1年次の「論理表現」の授業で週1時間実施していますが、内容は単なる文法学習ではなく、ネィテブであるJET指導員とともに、英語の微妙なニュアンスの違いなどに焦点を当て、アカデミックライティングを意識し、自分の言葉で発信していく力「実際に使える英語」を育てています。
Q11: 東京都次世代リーダープログラムによる留学へ、どのくらいの生徒さんが参加していますか。
A11:次世代リーダープログラムでは、北米地域(アメリカ合衆国、カナダ)に毎年2名程度の生徒が参加しています。また、民間の留学プログラムを利用して海外へ行く生徒もおり、それらを含めると年間で約5名程度の生徒が1年間の留学をしています。留学後の学年の扱いについては2通りあり、「留学扱い」とする場合は留学中の学習が単位として認められ、帰国後は元の学年に復帰できます。一方、「休学扱い」の場合は単位認定にはならず、一つ下の学年に戻ることになります。本校では、「留学」を「休学扱い」としている生徒が多い傾向にあります。これは、帰国後にもう1年間本校でしっかりさまざまな教科を学ぶことで、志望大学への進学に備えるためです。仮に1年間を「留学」による単位の履修に充て、学びが不十分なまま受験に向かうよりも、もう1年本校で過ごすことを選ぶ生徒が多く、その背景には浪人を避けたいという考えもあるようです。
👇後半はコチラ👇
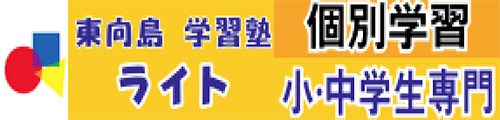


“【学校紹介】都立日比谷高等学校 前半 インタビュー” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。