【学校紹介】東京電機大学中学校高等学校 前半 インタビュー

学校紹介:インタビューNo.136
東京電機大学中学校・高等学校
小金井市梶野町4-8-1
『人間らしく生きる』
共学校

入試広報担当
池田 巧先生
👇👇👇インタビュースタート👇👇👇
✐✎✐✎まずは✐✎✐✎
Q1:1939年(昭和14年)に創立され歴史と伝統のある学校ですが、現在各学年何クラスあり、在籍は何名ですか。
A1:中学は33名前後の5クラス編成、高校は40名前後の7クラス編成です。
Q2: 男女の生徒数の割合を教えてください。
A2:男女比は2対1となっていますが、男女仲が良く、すぐに親しくなります。学校行事の委員長なども女子生徒が担うことが多くなっています。
Q3:御校の校訓は『人間らしく生きる』ですが、どのようなことに力を入れていますか。
Q4:自転車で通学することはできますか。
A4:可能です。
Q5:どのエリアから通ってくる生徒が多いですか
A5:埼玉県からは「さいたま市・所沢市・新座市」、23区からは「杉並区・世田谷区・練馬区」、多摩地域からは「八王子市・立川市・日野市・国立市」、本校近くの「小金井市・武蔵野市・三鷹市・府中市・小平市・国分寺市・西東京市」も多くの方々に通っていただいています。
✐✎✐✎中学校ついて✐✎✐✎
Q6:クラス編成について教えてください。
A6:一貫生は1クラス33名前後の5クラス編成で、現在は中学3年生で応用力養成クラス1つと、基礎力充実クラス4クラスに分かれます。高校へ進むと基礎クラスが1つ減り、40名前後の学級になります。高校2年生に上がるときに、理系と文系に分かれます。これは、高校入学生も同様です。一貫生と異なるのは、理系と文系の比率です。高校入学生の方が若干、理系が多くなります。東京電機大学への内部推薦を考える場合は高校2年生から理系クラスに所属してもらいます。
Q7:中学3年生から『基礎力充実クラス』『応用力養成クラス』に分かれますが、進級ごとにクラス分けはありますか。
A7:中学3年生から応用力養成クラスができ、中学2年・中学3年・高校1年の3回必ず入れ替えのタイミングが用意されています。一人ひとりのスイッチが入るタイミングが違うこともあり、毎年入れ替えるようにしています。こうした仕組みを通じて、意思決定の機会を設けるようにしています。
Q8:高校への入学試験はありますか。
A8:ありません。中学校3年間の成績や学校生活の様子などを総合的に判断しています。
Q9:高入生と同じクラスになりますか。
A9:なりません。カリキュラムが違うため、一貫生は6年間、高入生は3年間、その対象生徒でクラス替えをしていきます。
✐✎✐✎高等学校について✐✎✐✎
Q10:『応用力養成クラス』『基礎力充実クラス』に分かれていますが、それぞれの特徴を教えてください。
A10:応用力養成クラスは、中学3年進学時に基礎学力があり希望する生徒を選抜して編成され、国公立大学や難関私立大学への現役合格を目指して応用力を養うクラスです。発展的な内容を中心とした授業と到達度に応じた指導を行い、高校2年以降は志望に応じて文系・理系に分かれ、入試演習を通じて必要な学力を重点的に強化します。基礎力充実クラスは、生徒一人ひとりの学習段階に応じて基礎学力を着実に定着させ、学習意欲を高めながら希望進路の実現を目指すクラスです。放課後学習や個別指導も取り入れ、学び残しのない丁寧な指導を行います。高校2年以降は理系・文系のコース選択や自由選択科目を通じて目的意識を育み、大学受験に必要な学力を重点的に伸ばしていきます。
Q11:文理選択はいつですか。また文理の割合を教えてください。
A11:文理選択は、高校2年生から行われます。文理の割合は、理系:文系=7:3となっています。
Q12: 御校の授業の特徴があれば、教えてください。
A12: 本校の理科教育では、「見て・さわって・やってみる」ことで実感する学びを大切にしており、100以上の実験や観察を通して、生徒が主体的に科学と向き合う機会を提供しています。生物・物理・化学・地学(中学)の各分野にわたり、身近な現象や世界の仕組みを探究しながら、生徒の「なぜ?」に応える授業を展開しています。たとえば、生命の仕組みを観察し世界の見え方が変わる体験や、日常の中にある現象を物理で証明することで思考力を養い、化学では変化や反応を通じて新たな驚きを発見し、地学では地球の謎に迫る探究心を育てています。さらに、実験結果をレポートにまとめる活動を通して、論理的な思考力や表現力も身につけていきます。手作りの実験器具を用いた授業では、創造力や探究心を刺激し、学びへの主体的な姿勢を育成しています。こうした学びを積み重ねたうえで、高校では進路に応じた選択科目を設置し、大学入試を見据えた高度な学習へとつなげています。
本校の情報教育では、「表現力」を養うことを重視し、ソフト・ハードの両面からICT活用の力を育てています。40年以上にわたり蓄積された実績あるカリキュラムと、複数の専任教員による指導体制のもと、全学年で情報の授業を展開。1人1台のPC環境で、ロイロノートやプレゼンソフトなどを活用しながら、生徒が自分の意見や考えを主体的に表現し、他者と共有・協働する力を育みます。授業では、タイピング練習やプレゼンテーション、プログラミングなどのスキルを段階的に習得し、VBAやC#、Pythonといった言語にも触れる機会が用意されています。実際の授業では、マインクラフトの教育用ソフトを使ったプログラミング学習や、PowerPointを活用した英語でのプレゼンテーションなど、実社会にも通じる力を伸ばす多様な実践を通じて、生徒の自己表現と相互理解の両輪で「伝える力」を身につけていきます。
続きはコチラ👇
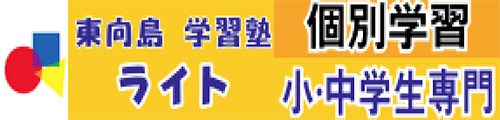


“【学校紹介】東京電機大学中学校高等学校 前半 インタビュー” に対して3件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。